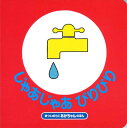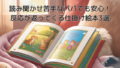![1歳児が絵本で笑っているイメージ]
「子どもが絵本に反応してくれない…」 「読み聞かせても無表情なことが多くて不安…」
そんな悩みを持つパパのみなさん、心配無用です!
こんにちは。5歳と1歳の男児を育てる父親で、元図書館司書として数年間、数千冊の絵本を見てきた私が、実際の育児体験とプロの知見を組み合わせて、1歳児が間違いなく笑ってくれる絵本3選をご紹介します。
今回ご紹介する3冊は、5歳の長男の時も効果を実証済みで、現在1歳の次男でも毎日の読み聞かせで大活躍している、まさに「パパ実証済み」の絵本です。図書館で多くの親子を見てきた経験からも、これらは「反応率100%」と言っても過言ではありません。
1. 『ぴょーん』〜体を動かして真似したくなる飛び跳ね絵本〜
著者: まつおかたつひで
対象年齢: 0歳〜2歳
読み聞かせ時間: 約2分
この絵本の最大の特徴は、「ぴょーん」という単純で楽しい擬音語とそれに伴う動きです。カエルなど様々な動物が「ぴょーん」と跳ねる様子が描かれており、読み手も実際に「ぴよーん!」と動いて見せることができます。
1歳児は言葉よりも動きで理解する時期。この絵本は視覚・聴覚・運動感覚をすべて刺激するため、全身で楽しめるのです。
我が家では。。。
5歳の長男の時代から愛用しているこの絵本、現在1歳の次男での反応は以下の通りです:
1歳2ヶ月当時、私が「ぴよーん!」と言いながら体を弾ませると、最初は不思議そうな顔をしていましたが、3回目には先回りして手をパタパタ。現在(1歳5ヶ月)では、本を持ってくると同時に「ぴ、ぴ!」と言いながら小さくジャンプしようとします。
長男の時も全く同じ反応だったので、この絵本の効果は確実だと感じています。
パパポイント: 恥ずかしがらずに大げさに「ぴよーん」と跳ねてみましょう。子どもは予想外のパパの行動に大喜びします!
2. 『じゃあじゃあびりびり』〜感覚を刺激する音の楽しさ〜
著者: まついのりこ
対象年齢: 0歳〜2歳
読み聞かせ時間: 約2分
この絵本は日常生活の様々な音をオノマトペ(擬音語)で表現しているのが特徴です。水の「じゃあじゃあ」、紙の「びりびり」など、赤ちゃんの周りにある音が次々と登場します。
1歳児は言葉の意味よりも音のリズムや抑揚に反応します。この本は音の世界を視覚的に表現しているため、彼らの「音と物の関係づけ」という重要な認知発達を楽しく刺激するのです。
我が家では。。。
「じゃあじゃあ」のページでは必ず指差しをし、実際にお風呂で水を見ると「じゃじゃ!」と言うように。「びりびり」のページでは両手をひらひらさせて紙を破るような動作を繰り返します。
さらに驚いたのは、息子が本に出てくる音を実生活で見つけた時の反応。車の「ぶーぶー」を聞くと、必ず絵本のページを思い出すような表情を見せるんです。
パパポイント: 絵本の音に合わせて手や体を動かすと反応倍増!実際の生活場面でも「ほら、じゃあじゃあだね」と言うと認知発達にも◎
3. 『いないいないばあ』〜永遠の名作!笑顔を引き出す基本書〜
著者: 松谷みよ子
対象年齢: 0歳〜2歳
読み聞かせ時間: 約3分
「いないいないばあ」は、世界中の赤ちゃんが反応する普遍的な遊びを絵本にしたもの。この本が特別なのは、予測と驚きのリズムが絶妙に組み込まれていることです。
子どもたちは「いないいない…」の間に期待感が高まり、「ばあ!」の瞬間に喜びを爆発させます。これは心理学的には「対象永続性(見えなくなったものも存在し続けるという認識)」の発達を促す重要な遊びなのです。
我が家では。。。
長男の時も、次男の時も、初めて読んだ時の反応は同じでした。現在1歳5ヶ月の次男の様子:
「いないいない…」のタイミングで、自分も顔を手で隠そうとする。「ばあ!」の瞬間は必ず笑顔。最近では私が言う前に「ばぁ!」と先に言ってしまうことも。
特に効果的だったのは、本の「いないいない…」のタイミングで、実際に私も顔を隠し、「ばあ!」で顔を出すという組み合わせ。息子は毎回、お腹を抱えて笑います。
パパポイント: 読み方のバリエーションを増やしましょう。「いないいない」をゆっくり言って期待感を高めたり、「ばあ!」で顔を近づけたりすると、さらに反応が良くなります。
1歳児が反応する絵本の特徴とは?
なぜこの3冊が特に1歳児に響くのか、父親として二人の息子に読み聞かせをしてきた経験から、その共通点を分析してみました:
- 繰り返しのある単純な言葉 – 言葉の習得段階にある1歳児は、単純で繰り返される言葉に反応します
- リズム感のある擬音語・擬態語 – 「ぴよーん」「じゃあじゃあ」などの音のリズムが脳を心地よく刺激します
- 予測可能な展開と小さな驚き – パターン化された展開の中に小さな変化があることで、認知発達と情緒発達の両方を促します
- 動きを誘発する内容 – 体を動かしたくなる要素があり、全身で楽しめる本は特に効果的です
これらの要素は、まさに1歳児の発達段階に合致しています。言葉よりも感覚で世界を理解している時期だからこそ、これらの絵本は強く響くのです。
まとめ:笑いを引き出す絵本で親子時間を充実させよう
今回ご紹介した3冊はいずれも、我が家で長男・次男と実際に使ってきた「効果実証済み」の絵本です。特にパパの皆さんにとって重要なのは、これらの絵本を読む際に「恥ずかしがらない」こと。大げさに声を変えたり、体を動かしたりすることで、お子さんの反応は格段に良くなります。
5歳の長男と1歳の次男、5歳の年齢差がありながら同じ絵本で笑顔になる姿を見ていると、本当に良い絵本は時代や年齢を超えて愛されるのだと実感します。
ママより読み聞かせの経験が少ないパパだからこそ、この3冊から始めれば失敗なし。お子さんの笑顔と、それに続く「もう一回!」という要求に、読み聞かせの楽しさを実感できるはずです。
そして何より、この時期のたっぷりとした笑いの体験は、お子さんの情緒発達の土台となります。楽しみながら脳の発達も促せる絵本との時間を、ぜひ大切にしてくださいね。
この記事の絵本は全て実際に我が家の息子たちのリアクションを確認した体験に基づいています。子どもの性格や好みによって反応は異なりますが、多くの子どもが楽しめる内容となっています。